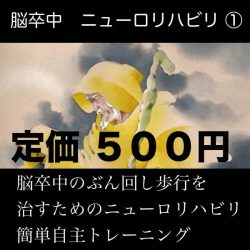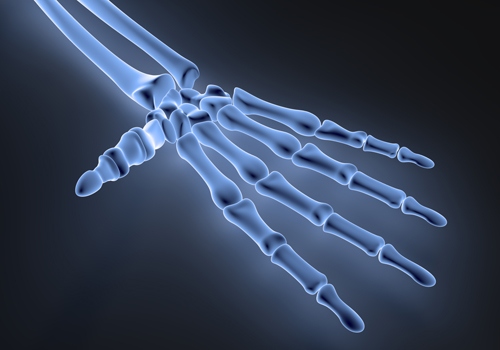『悲報』脳卒中の日常生活動作訓練が片麻痺の回復を妨げることについて!
日々進歩してコロコロ変わる脳科学の常識に翻弄され、これからご自分の脳卒中リハビリテーションをどうすればいいのか、出口の見えない不安に苛まれている皆様。
こんにちは!
ガチガチの運動機能改善型セラピストの松澤です( ´ ▽ ` )ノ
あれ! なんかムッとされてます!
実は今回の記事は半年に一回くらいをめどにお送りしている「毒吐きタイム」の記事なのです。
そんなこと言ってお前さんはいつも辛辣なことを言いまくっているだろうって。
いえいえ、そんなことはありません。
普段の私のはあくまで「鋭い意見」であって、感情的にキツイことを言ったことは、これまで一度もありません。
実はここ数ヶ月の間、かなりの数の脳科学に関する文献や専門書を読み漁ってきましたが、その結果感じたことがあるのです。
それは
「やはり今から脳卒中リハビリテーションの大きな転換期が来るだろう」
と言うことです。
そしてしばらくの間は時代の波の中で皆さん右往左往するのではないかしら?
などと少し心配にもなったりしています。
なので今回は皆さんがいろいろ考えちゃうだろうなと思いながら記事を書かせていただいています。
回復期リハビリテーション病院での脳卒中リハビリは日常生活動作訓練が主流です
現在の回復期リハビリテーション病院での脳卒中リハビリは主に日常生活動作訓練が行われています。
これには立派な理由があって、現在の高齢者がドンドン増えている状態で、昔のように2年も3年も入院して脳卒中リハビリを受けていただくことは経済的に無理なのです。
何せ一ヶ月入院してリハビリを行うと、一人当たり約70万円も掛かるのです。
ですから脳卒中の超急性期の治療が終わってから数ヶ月の、見かけ上の麻痺の回復が一番良い時期に、日常生活動作訓練に特化して在宅での生活の自立を図ることで、早期退院と在宅復帰率を高める狙いがあるのです。
そして日常生活動作訓練を中心としたリハビリテーションの戦略の基本として「日常生活動作を行うことで運動機能を高めていく」というものがあります。
これまでの常識では「一度破壊された脳神経細胞は二度と再生しない」つまりは「麻痺は治らない」のですから、麻痺が治らないことを前提にして、残された運動機能を最大限高めていく日常生活動作訓練型のリハビリテーションは十分理にかなっていたのです。
21世紀に入って脳科学が大きく進歩しました
21世紀の科学に残された最後のフロンティアが脳科学と言われています。
そして21世紀に脳科学が大きく進歩した結果として「脳卒中の麻痺が回復する可能性がある」ことが分かってきたのです。
また脳神経が運動をコントロールする機構が明らかになるにつれて、運動機能を高めるためにはどんな運動方法が最適なのかが分かってきたのです。
そして「ただがむしゃらに日常生活動作訓練を頑張る」ことは、必ずしも脳卒中の片麻痺を回復したり、運動機能を高めることにはならないと言うことも分かってきてしまったのです。
でもそれってよく考えてみれば当たり前のことですよね!
ただ日常生活動作の訓練をすれば良くなるなら専門家は必要ないじゃんってことですよね。
「家政婦のミタにでもリハビリして貰えば良いじゃん!」てなりませんか?
(~_~;).。o○(今回はかなり毒吐いてるな)
でも本当は脳卒中片麻痺の運動機能を改善するためには、結構専門的な知識と技術が必要なんですよ!
日常生活動作訓練が運動機能の改善を妨げる例
日常生活動作訓練が運動機能の改善を妨げる一番身近な例としての「歩行練習」
皆さんが脳卒中の急性期に入院していて、一番になんとかしたいと思うことは大体が同じです。
「自分で歩いてトイレに行きたい」ですよね!
そうしないといちいちナースコールを押して看護師さんを呼んで尿瓶を当ててもらわなくてはならないからです。
これは結構辛いものがあります。
またオムツの中に便をするのもキツイですよね。
人間の尊厳に関わる重大事です!
ですから「とにかく歩けるようになろう」とします。
これ自体は決して間違いではありません。
歩かなければベッド上で寝たきりになって体力が落ちてしまいますから。
しかし麻痺によって股関節や膝関節が十分に動かせない状態で、無理やりに歩こうとすることで「ぶん回し歩行」などの脳卒中片麻痺に特徴的な異常歩行パターンを身につけてしまいます。
そして一度身につけた異常な歩行パターンは、ただ歩く練習を繰り返しただけでは、決して改善されません。
その理由はそれがそのまま「その異常な歩行パターンを練習する」ことになるからです。
つまり普段あなたが行っている歩行練習は、日常生活動作訓練としての、ただ歩くだけの歩行練習であって、異常な歩行パターンを改善するための戦略的な歩行動作のリハビリアプローチにはなっていないと言うことなのです。
ですからキチンとした歩行能力を改善するためのリハビリアプローチを行わないで、ただ歩くだけでは、その異常な歩行パターンをより上手になる練習をしていることになってしまいます。
頑張って歩く練習をしていれば、いつかは上手に歩けるようになると信じて毎日歩行練習をしている方にとっては、これは衝撃的な事実だと思います。
日常生活動作訓練として健側の手ばかり使うこと
もう一つ日常生活動作訓練の問題点を、今度は上肢の手の機能の視点から解説したいと思います。
日常生活動作訓練型のリハビリテーションの特徴として、麻痺側の手へのアプローチより、健側の手を積極的に使って日常生活動作を自立させようとすることが挙げられます。
確かにいったん動かせなくなった麻痺側の指先がすぐに器用に動かせるようになって、実用的に使えるようになるなどということは、まずありません。
ですから日常生活動作をなるべく早く自立させるために、健側の手の動作を工夫して、片手でも自立した生活ができるように練習していくのが一般的なアプローチになっています。
そして自宅に戻ってからは、本当に麻痺側の手を意識することも少なくなって、健側の手ばかり使うようになります。
しかしここに大きな落とし穴があるのです。
私たちの脳は左右の大脳半球に分かれています。
そして右の大脳半球は左の大脳半球の活動を抑えようと作用しており、逆に左の大脳半球は右の大脳半球の活動を抑えようとしています。
そうなのです左右の大脳半球はお互いに相手の活動を抑え込もうとする、相互に抑制し合う神経制御のシステムを持っているのです。
ですからあなたが健側の手ばかりを使っていると、健側の大脳半球の活動ばかりが高まって、その影響で、健側大脳半球から麻痺側の大脳半球への抑制がドンドン強くなってしまいます。
そうすることで麻痺側の神経活動が抑制され、麻痺の回復や運動機能の向上がさらに後退してしまうのです。
この麻痺側の大脳半球への抑制作用は、手の機能だけでなく足の機能も抑制しますし、その他の理解力や判断力に影響を与える可能性もあるのです。
また麻痺側の指を動かさないで放置することで、さらに麻痺側の手の麻痺や感覚障害が強くなることも分かってきています。
ですからこれからは「すぐには役に立たなくても」麻痺側の手のリハビリテーションを欠かすことは出来なくなってきているのです。
まとめ
今回は詳しい神経学的な説明は省略しましたが、これまでの日常生活動作訓練型のリハビリテーションアプローチから、今後の脳科学に基づく新たな脳卒中リハビリテーションへの転換期が来ていることを簡単にご説明しました。
今後さらに脳科学が進歩するうちに、ドンドン新しい脳卒中に対するリハビリテーションアプローチが生み出されてくるようです。
あなたもこの流れに乗り遅れないように、しっかり情報を集めて頑張ってリハビリテーションを行っていってくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございます!