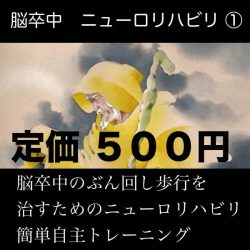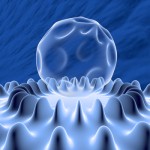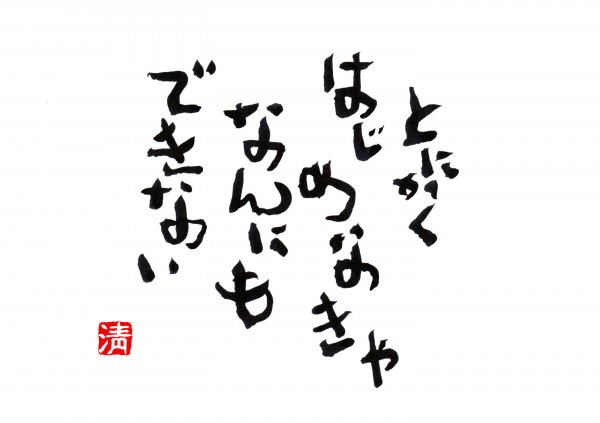はじめに
はじめにパーキンソン病とはどんな病気かについて一度簡単におさらいをしておきたいと思います。
パーキンソン病とは!
パーキンソン病は、Lewy小体(レヴィ小体)という物質が脳内の、特に中脳の黒質に溜まることによって、黒質からのドーパミンという神経伝達物質の分泌量が減少することで、同じ神経伝達物質であるアセチルコリンとのバランスが悪くなり、振戦や固縮やすくみ足などの運動症状が発症します。
パーキンソン病の症状であるパーキンソニズムの症状は、① 安静時振戦 ② 筋強剛 ③ 無動 ④ 寡動 ⑤ 姿勢反射障害が挙げられます。
ドーパミンとアセチルコリンは、互いに拮抗して相互に抑制し合う関係にあり、お互いの作用が強くなりすぎないように調整し合う関係と言えます。
ですからドーパミンが減少してアセチルコリンが多くなると運動症状が出てパーキンソン病になります。
またドーパミンが多くなりすぎてアセチルコリンが足りなくなると統合失調症という精神疾患となり幻覚や幻視などが起こります。
ですからパーキンソン病薬の副作用で、ドーパミンが過剰になると時には幻覚や幻視などが起きる場合があるのです。
パーキンソン病の発症
パーキンソン病の発症は、振戦や動作の巧緻性低下(動作拙劣・動作緩慢)などの運動症状で始まることが多く、場合によっては肩関節周囲炎や腰痛などの痛みの症状から始まって、筋肉の固縮や振戦などの症状が出る場合があります。
パーキンソン病では、すくみ足や転倒しやすい等の姿勢反射障害が最初に出ることは、まずないと言われており、もしすくみ足や易転倒傾向から症状が始まった場合は、同じようなパーキンソン症候群を呈する病気である、進行性核上性麻痺(PSP)や大脳皮質基底核変性症(CGB)などの別の神経難病の可能性があります。
これらの病気はパーキンソン病よりもずっと進行が早いので注意が必要です。
もし不安な場合は専門の神経内科の先生にご相談してみてください。
パーキンソン病の発症例
-
振戦で発症 → 動作の巧緻性低下(動作拙劣・動作緩慢)
-
肩や腰の痛みで発症 → 振戦や固縮
※ すくみ足や易転倒傾向等の姿勢反射障害で発症 → PSPやCGBなどの別の神経難病の可能性がある
パーキンソン病の進行
パーキンソン病は、脳内にLewy小体(レヴィ小体)が溜まっていくことで進行しますから、その進行はゆっくりしています。
一般的には運動症状は片側の手(上肢)または足(下肢)から始まって、1年から数年かけて反対側にも運動症状が出るようになっていきます。
麻痺の左右差はなくなる場合も残る場合もあります。
進行には個人差はありますが、だいたいは最初の10年は若干の不自由はありますが働くことが可能です。
つぎの20年目には自宅内で介助を受けながら、ほぼ自立した生活を送ることができます。
つぎの30年目にはベッドで寝たり起きたりの状態になり、介護が必要になります。
振戦で発症した場合は進行が遅くなる傾向があり、動作の巧緻性低下(動作拙劣・動作緩慢)で発症した場合は進行が早くなる傾向があると言われています。
20年目の自宅内で自立した生活を送っている方が、肩や腰の痛みが強くなって起きていられなくなり、急に寝たり起きたりの生活に陥ってしまう場合がありますが、これはパーキンソン病の急激な進行ではなく、筋肉のコンディションの悪化と痛みの増強による、身体機能の悪循環スパイラルに陥ったことが原因ですので、リハビリテーションにより改善することができます。
パーキンソン病の進行例
Lewy小体(レヴィ小体)の出現
-
迷走神経背側核と嗅球に出現
-
ついで後下部脳幹と中脳黒質に出現して運動症状を発症
-
前脳基底部、側頭葉皮質、大脳部皮質に出現して精神症状や非運動症状を発症
※ ちなみにLewy小体(レヴィ小体)がはじめに前脳基底部、側頭葉皮質、大脳部皮質に出現して神経症状や非運動症状を発症する事があり、この場合はレヴィ小体型認知症と呼ばれる認知症を発症して、あとからパーキンソン病などの運動症状が出てきます。 パーキンソン病とレヴィ小体型認知症は兄弟のような関係にあります。パーキンソン病の中で③の前脳基底部、側頭葉皮質、大脳部皮質に出現して神経症状や非運動症状を発症するのは全体の3割程度と言われており、残りの7割の方は精神症状を発症することは無いようです。
※ パーキンソン病の中で③の前脳基底部、側頭葉皮質、大脳部皮質に出現して神経症状や非運動症状を発症するのは全体の3割程度と言われており、残りの7割の方は精神症状を発症することは無いようです。
パーキンソン病の進行速度
-
振戦で発症した場合 → 進行が遅くなる傾向がある
-
動作の巧緻性低下(動作拙劣・動作緩慢)で発症した場合 → 進行が早くなる傾向がある
パーキンソン病の症状
運動症状
-
振戦: 4~5Hzの安静時振戦で動作時には消失します
-
筋強剛: 歯車様筋強剛(他動的に動かされるとカクカクと抵抗がある)、鉛管様筋強剛(他動的に動かされると常に一定の抵抗がある)
-
体幹運動低下: 背骨などの体幹の動きが悪くなり、寝返りなどの基本動作ができにくくなる。 そのため歩けても寝返りできない、起き上がれない等の現象が起きる。
-
姿勢反射障害: 初期にはないが、発症数年後からすくみ足や転倒しやすくなるなどの症状が起きる。
-
不随意運動(ジスキネジア): パーキンソン病が進行してきて、L-dopaの効きが悪くなり、ドーパミンの投与が過剰になるとジスキネジアと呼ばれる不随意運動が起きやすくなります。
その他の症状
-
ウェアリングオフ現象: 中脳黒質で作られたドーパミンは線条体に送られて貯められますが、パーキンソン病が進行すると、線条体が萎縮して投与されたドーパミンが貯められなくなり、途中で薬の効果が切れる現象が起こります。 この場合は一回の服薬量を減らし、服薬回数を増やします。
-
意欲の低下: ドーパミンが低下すると中脳腹側被蓋部から側座核・前頭葉の回路がうまく機能しなくなり意欲の低下が起こります。
精神症状
Lewy小体(レヴィ小体)が前脳基底部、側頭葉皮質、大脳部皮質に出現すると神経症状が起こります。
-
意識レベルの変動
-
認知機能障害
-
幻視
-
妄想
-
思考が遅くなり決断できなくなる
-
記憶は悪くならない?
パーキンソン病薬の副作用での幻覚・妄想
Lewy小体(レヴィ小体)の前脳基底部、側頭葉皮質、大脳部皮質への出現だけでなく、ドパミン製剤や坑コリン薬でも幻覚・妄想などの精神症状が起きる場合があります。 また外科手術による定位電気脳刺激手術(DBS)によっても精神症状が出現する場合があります。 これらの場合は主治医の先生とよくご相談されてください。
非運動症状
Lewy小体(レヴィ小体)が前脳基底部、側頭葉皮質、大脳部皮質に出現すると以下の様な非運動症状が起こります。
-
脱抑制: 衝動制御障害により怒りやすくなります
-
反復常同行動: 特に必要のない行動をずっと繰り返す様になります
-
ドパミン調整異常症候群: ドバミン製剤の服用に依存して過剰に服用する様になります
-
睡眠障害: 日中の過剰な睡眠や夜間睡眠中の行動の異常(REM睡眠行動異常)
-
自律神経障害: 血圧の変動や起立性低血圧、頻尿や乏尿、切迫膀胱、便秘、発汗異常など
-
嗅覚の低下
-
痛みやシビレ
-
下肢の浮腫
多彩なパーキンソン病の症状
パーキンソン病は単なる運動症状を起こす病気ではなく、様々な全身的な症状を引き起こす病気です。 そのため、その病態から悪循環のスパイラルを引き起こしやすいため、パーキンソン病の進行とは言えない様な痛みや運動機能の低下を引き起こすことが多く、それらがパーキンソン病のリハビリテーションの大きな課題ともなっています。
今後はこれらの問題を解決してパーキンソン病による痛みや運動機能の低下を防ぐためのリハビリテーションや、パーキンソン病の進行に対抗するための運動方法などに対する解説を行っていきたいと思います。
次回は
「大脳基底核と視床のはなし」
についてご説明します。
最後までお読みいただきありがとうございます
注意事項!
この運動は、あなたの身体状態を評価した上で処方されたものではありません。 ご自身の主治医あるいはリハビリ担当者にご相談の上自己責任にて行ってくださるようお願い申し上げます。
関連ページ
序章: その運動機能の低下は本当にパーキンソン病の進行ですか?
1. パーキンソン病のリハビリテーション はじめに
2. パーキンソン病とはどんな病気かのおさらい
3. 大脳基底核と視床のはなし
4. パーキンソン病による悪循環スパイラルとそれを改善するリハビリテーション
5. パーキンソン病の大脳基底核と視床のコントロールを良くするための運動方法の考え方