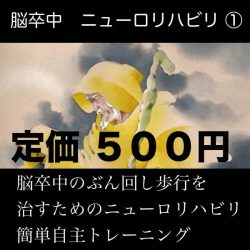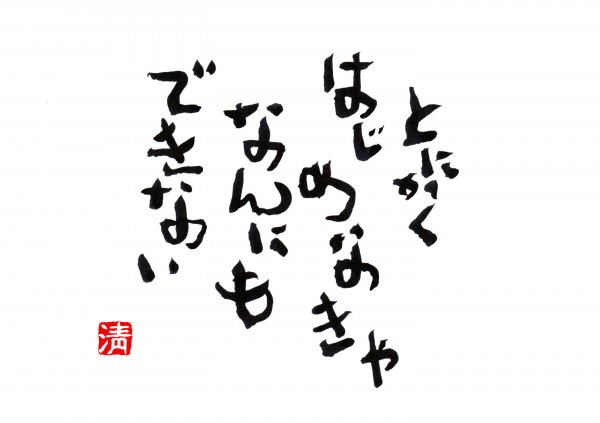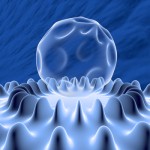脳卒中片麻痺の足や手の浮腫を解消するリハビリ方法
はじめに
脳卒中では手足の抹消、つまり指先や足首から先の足底や足背が浮腫むことが良くあります。
この浮腫があると、とにかく不快ですし、筋肉や関節が強張って動きが悪くなったりします。
また浮腫によって指先や足底の感覚が鈍くなると、指先の運動制御が上手くできなくなったり、歩行バランスが取りにくくなったりします。
そうなるとリハビリテーションによる麻痺の回復に重要な、運動学習の効果も低下してしまいます。
また手足の浮腫は心不全や栄養障害などの、重大な身体状態の問題を表すシグナルだったりします。
ですから決して疎かにして良いものではありません。
今回はこの手足の浮腫について、その原因と対策およびリハビリテーションの方法について解説したいと思います。
手足が浮腫む原因はナニ?
脳卒中片麻痺になって手足が浮腫む経験をする方は結構多いようです。
あなたはどうですか?
手足に浮腫はありませんか?
はじめに脅かしてしまいましたが、ほとんどの浮腫は適切な運動で解消できるような浮腫ですから心配は要りません。
しかし中には注意を要する浮腫もありますので、その辺りも含めて浮腫が起きる様々な原因についてお話ししたいと思います。
心不全からくる手足の浮腫
いきなり大ネタから入ってしまい恐縮です。
ですが心不全による浮腫をキチンと理解して、早期に問題を発見できれば、とても大きなメリットになります。
心不全傾向というのは、心筋梗塞などの急性に発症する病気とは異なり、時間をかけて進行してくる場合が結構あります。
ですからそうそう無いとは思いますが、もしかしたらの心不全を早期に見極めるための手足の浮腫の特徴について少し解説いたしますね。
心不全とは!
心不全による浮腫のお話をする前に、少し「心不全」についておさらいをしておきましょう。
心不全というのは、いわゆる診断名ではありません。
診断名ではなく心臓の機能の状態を表すものなのです。
つまり「心筋梗塞」や「不整脈(色々な種類があります)」は診断名です。
それらの心筋梗塞や不整脈によって、心臓の血液を送るポンプ機能が低下して、脳や全身の臓器に十分な血液を送れなくなった状態が「心不全」と言います。
すなわち心臓に酸素と栄養を送る冠動脈が詰まると、心筋に血液が届かなくなり、心筋が壊死してしまい「心筋梗塞」になります。
その結果として、壊死した心筋が動かなくなることで、心臓のポンプが上手く働かなくなり「心不全」の状態になるのです。
ですから以前に心筋梗塞に罹ったことがある方や、動脈硬化によって、心臓の血管が細くなり「狭心症」の傾向がある方などは、日常生活の中で、いつの間にか慢性的に心不全傾向が進んでおり、手足が浮腫んでいるリスクが高いのです。
どうして心不全で手足が浮腫むのか?
ではどうして心不全になると手足が浮腫むのでしょう?
実は心不全になって心臓が脳や全身に血液を十分に送れなくなると、身体は自動的に重要な臓器に優先的に血液を送るように調節するようになります。
この時に重要な臓器とは、「脳」と「心臓」と「肺」ですね、とにかくこの3つは最後まで頑張って血液を送って守ろうとします。
しかしその反面で手足の先などは、真っ先に血液が届かなくなります。
ですから急激に心不全になると、指先が真っ青に冷たくなる「チアノーゼ」が起こります。
しかし日常生活で慢性的にゆっくりと心不全が進行した場合は、手足の「チアノーゼ」は目立ちません。
それに対して、腎臓への血液の流れが少なくなります。
要するに脳や心臓に血液を送るために、腎臓への血液の流れを減らしてしまっているのです。
しかし腎臓に血液が流れないと、腎臓で血液をろ過して「おしっこ」を作ることができなくなります。
そしておしっこが少なくなったのに気づかずに、水を飲み続けていると、体のかなに余分な水分が溜まってしまいます。
そうして手足が浮腫むようになるのです。
これは非常に危険な心不全の兆候ですから、十分な注意が必要です。
心不全で手足が浮腫んでいるとどんなことが起きますか?
心不全によって手足がむくんでいる方の特徴としては、夜中におしっこに起きる回数が増えることがあります。
この理由は、昼間は起きているために、体内の余分な水分は足の方に溜まって浮腫んでいます。
しかし夜になって寝床で横になっていると、心臓と脳と足が水平で同じ高さになるために、心臓が高い場所にある脳に頑張って血液を送らなくても済むようになります。
そして足からも楽に余分な水分が心臓に向けて戻ってきます。
ですから心臓に対する負担が軽くなり、その分は腎臓に血液が送られるようになります。
その結果として、夜中におしっこの量が増えて、トイレの回数が増えるのです。
トイレの回数が増えるだけで心不全を心配する必要はありませんが、足の浮腫が強い方で、夜中のトイレが増えてきた場合は十分に注意して、必要であれば主治医の先生にご相談くださいね。
よろしくお願いします。
注意すべき心不全からくる浮腫への対応方法は?
心不全が原因で手足がむくんでいる場合には、リハビリテーションはあまり役に立ちません。
主治医の先生の指示に従い、きちんと内服でおしっこの管理や心臓の管理をしてもらいましょう。
栄養障害からくる手足の浮腫!
手足が浮腫む原因として、心臓の機能以外に内臓機能が関わっているもう一つの浮腫があります。
それが栄養障害からくる浮腫です。
栄養障害といっても、主に手足のむくみの原因になるのは「タンパク質」が足りないことです。
食事が偏ったり、消化器からの栄養の吸収が低下して、血液中のタンパク質が不足すると、手足が浮腫んでしまいます。
なぜ血液中のタンパク質が不足すると手足が浮腫むのか?
なぜ栄養が不足して、血液中のタンパク質が減ると手足が浮腫むのでしょうか?
それは血液中のタンパク質が減ると、血液中の水分が血管の外に漏れ出してしまうからです。
どうしてかというと、あなたは血管がしっかりした血液を流すための管だと思っていますよね。
でもね、血管の一番先にあるのは「毛細血管」ですよね。
そして毛細血管には細胞に水分や栄養分を送り込むための細かい孔が開いているのです。
放っておくとこの孔から水分がどんどん漏れ出してしまいます。
でも血管の中には血液がきちんと流れていて、血液は液体がほとんどなので、水分は血管内に保たれていることになります。
どんな仕組みで先端が孔だらけの血管の中に血液が残っているのでしょう?
それは浸透圧を利用しているのです。
要するにセロファン紙などの細かい穴があいた幕の両側に、塩水と真水を入れておくと、塩水の方が浸透圧が高いために、水分が塩水の方に移動して、そちら側の水位が上がる実験があります。
私たちの血管もこの原理を利用して、血管内に血液の水分を引き留めているのです。
でも毛細血管の穴は、細胞に栄養を届けるために、水分の他に、塩分や糖分、さらにはアミノ酸まで通過させてしまいます。
ですから毛細血管の孔を通過しない物質の浸透圧が必要になります。
これがアルブミンやグロブリンなどの血液内のタンパク質による膠質浸透圧と呼ばれる作用になります。
つまり血管内に水分を引き込んで、血液をサラサラにしているのは、アルブミンやグロブリンなどのタンパク質成分なのです。
ですから栄養が不足して、血液内のアルブミンやグロブリンが不足すると、血液内の水分が細胞の周囲に流れ出して、手足が浮腫んでしまいます。
反対に血管内の水分が不足して、血液はドロドロになってしまっていますから、手足が浮腫んでいるからといって、血液の水分量が足りているとは限りません。
ですからこの状態で浮腫を減らそうとして、飲み水を減らしたりすると、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高めてしまいます。
この場合は食事バランスに気をつけて、必要に応じて主治医の先生に相談して、栄養の補助を行うことも効果的です。
とにかく栄養はとても大切です。
病気になったり、歳をとると、食欲が低下して、食事がおろそかになりやすいので、本当に注意して下さいね。
食事は薬と同じくらい大切です。
筋肉と自律神経のコンディションによる手足の浮腫について!
ここら辺りから、本格的にリハビリテーションが関与する浮腫の話になってきました。
脳卒中片麻痺になると手足の浮腫が起こりやすくなります。
特に急性期には、脳の神経活動が混乱するために、運動神経や感覚神経だけでなく、自律神経の機能も障害されてしまいます。
その結果として、手足などの抹消の血流が停滞して浮腫になることがあります。
筋コンディションの問題
またその浮腫が手足や背骨を支える筋肉に起こることで、筋肉が強張って動かしにくくなることで、さらに筋肉のポンプ作用が失われて、浮腫が悪化します。
この筋肉のポンプ作用というのは、手足の血管のうちの動脈は平滑筋と呼ばれる筋肉で出来た管で、自分で脈打つことで、血液を流すことができます。
しかし静脈は、逆流を防ぐための弁が付いただけの管で、自分で脈打って血液を流すことはありません。
この静脈の血液を流す仕組みが、筋肉が収縮することで、静脈を圧迫したり緩めたりすることで、血液を流します。
筋肉が強張って動かなくなることで、この筋肉によるポンプ作用が働きにくくなってしまいます。
このために手足が浮腫みやすくなります。
脊柱起立筋群と自律神経(交感神経)の関係
また背骨を支える「脊柱起立筋群」と呼ばれる筋肉が強張ることで、背骨の脇を並走している自律神経(交感神経)が緊張して、さらに手足の抹消の血流が抑制されるようになります。
交感神経は、血圧を高めて、脳や心臓に十分な血液を送るために、手足の抹消への血液の流れを制限して、その分を脳や心臓に送る働きがあります。
そのために交感神経が緊張すると、手足の血液の流れが障害されてしまいます。
このようにして、脳卒中になると神経の活動としても、筋肉のコンディションとしても、手足などの抹消が浮腫みやすくなるのです。
リハビリテーションで手足の浮腫を軽減する方法について!
心不全からくる手足の浮腫のケア方法
心不全が原因で手足がむくんでいる場合には、とにかく心不全に対する適切なケアが必要になります。
心不全に対するケアとしては
⑴ 心不全の原因となる心疾患の治療
⑵ 不整脈などの治療
⑶ 水分摂取量などをきちんと管理する
などが大切になってきます。
基本的には主治医の先生の指示に従ってください。
心不全傾向が強くなると
⑴ 体重の急激な増加(朝起きて昨夜より1~2kg増えている)
⑵ 指先や足底の浮腫
⑶ まぶたの浮腫
⑷ 指先のチアノーゼ
⑸ オシッコが少なくなる
などが起こりますので、一つの合図として、心臓に持病がある方は、日頃から注意しておくと良いでしょう。
栄養障害からくる手足の浮腫のケア方法
栄養障害による浮腫は、基本的には血液中のタンパク質成分である、アルブミンやグロブリンが減少してしまうことで、血管の中の血液から水分が周囲の細胞のサードスペースに流れ出して起こります。
血液の中のアルブミンなどの血漿タンパク質は、身体に対する栄養素が不足すると、分解されてアミノ酸になり、栄養として使われてしまいます。
ですから栄養障害による浮腫を予防するためには、普段の食生活を注意して、タンパク質やビタミン類のバランスが取れた食生活を取る必要があるのです。
普段の食事のバランスが崩れていると感じたら、栄養士さんなどに相談してみても良いと思います。
普段お世話になっている主治医の先生や看護師さんに相談してみてください。
筋肉と自律神経のコンディションによる手足の浮腫のケア方法
筋肉の強張りや自律神経機能の乱れに伴う手足の浮腫を改善するには、該当する手足の抹消の筋肉に対するコンディショニングをきちんと行う必要があります。
特に麻痺側の指先の筋肉の強張りは、麻痺側の上肢全体の強張りを強めていき、浮腫を増悪させる可能性があります。
また麻痺側の足の筋肉も、筋緊張が高まりやすく、指先などが強張りやすいため、それが原因となって浮腫が悪化する場合があります。
今回はそれらの問題を改善する方法として以下の2つの方法をご紹介します。
⑴ ミラクルグリップで麻痺側の手指の強張りを軽減して浮腫を改善する方法
本来なら筋肉が緊張して強張っている麻痺側の手指に何かを握らせることは、把握反射を促して、さらに指を強張らせてしまうため、行ってはいけません。
よく指が曲がらないように、丸めたタオルなどを握らせているケースを見かけますが、あれは間違いです。
さらに指が強張ってしまうので直ぐに止めましょう。
ここでご紹介する「ミラクルグリップ」は、特殊な高反発素材を利用して、グリップを作っています。
そのためにこのグリップを麻痺側の指に握らせると、反射的に握ってきた指を「高反発素材」が押し返します。
すると押し返されたことで、再び麻痺側の指がグリップを反射的に握ります。
するとまた反射的に握ってきた指を「高反発素材」が押し返します。
これをずっと繰り返すことで、一日中細かい指の屈伸運動を自動的に繰り返すことになります。
この屈伸運動の繰り返しが、麻痺側の強張った手指の筋肉をほぐして柔らかくしていくのです。
基本的にはミラクルグリップを握らせておくだけで、麻痺側の浮腫や緊張が低下していきます。
ミラクルグリップはこちらから購入できます
 |
【ホワイトサンズ】ミラクルグリップ MG40 2個入【クッショングリップ】【拘縮】【抗菌】【消臭】【手】【水洗い可能】 価格:3,880円 |
⑵ JPクッション上での立位バランス練習で足底の浮腫を改善する方法
足底の浮腫を軽減するために、手の時と同じように「高反発素材」を利用したクッションの上で立位練習を行います。
この「高反発素材」を利用した『JPクッション』は『ミラクルグリップ』とまったく同じ素材を使用しています。
じつは元々はこちらの『JPクッション』の方が元祖なのです。
このクッションの上に立ってみた感想は、少し硬めの砂浜の砂の上にいる感じでしょうか?
ほんのわずか足元がグラグラする感覚があります。
このクッションは、私が知る範囲では「浅田真央」さんがトリプルアクセルのトレーニングに使用していたのを確認しています。
トップアスリートの中にも愛用者が沢山いるようです。
このクッションの上で一日5分程度立位を行います。
もし可能であれば、左右の足への体重移動を交互に行うとさらに効果的です。
これを毎日繰り返すだけです。
簡単でしょう!
JPクッションはこちらから購入できます

  |
|
インナーマッスルを鍛える JPクッション (色は選択出来ません) https://www.youtube.com/watch?v=E-ZoHFVgV1k 新品価格 |
![]()
まとめ
脳卒中になると手足の浮腫が起こることがあります。
この浮腫は放置すると、さらに筋肉のコンディションを悪化させて、手指の運動を阻害して麻痺の回復を妨げたり、足底の感覚を阻害して歩行バランスを悪化させたりします。
これらの手足の浮腫の原因には、⑴ 心不全によるもの ⑵ 栄養障害によるもの ⑶ 筋コンディションと自律神経機能の障害によるものなどがあり、それぞれに対応方法が異なります。
手足の浮腫があることで、脳卒中リハビリテーションの効果が妨げられる可能性があります。
しかし日常のケアで手足の浮腫をキチンとケアすることで、リハビリテーションによる運動機能や麻痺の改善効果をより高めることができます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
注意事項!
このサイトでご紹介している運動は、あなたの身体状態を評価した上で処方されたものではありません。 ご自身の主治医あるいはリハビリ担当者にご相談の上自己責任にて行ってくださるようお願い申し上げます。